小学校受験の第一ステップとして誰もが避けては通れないのが願書の作成です。たかが願書と侮っていると痛い目を見ることになりかねませんので、ここでは自分の経験を踏まえて押さえておいた方がよいポイントについてご紹介します。
願書の重要性とは?
小学校受験では、願書だけで落とされてしまうということは、基本的にはありません。
願書を出せばほとんどの場合には試験を受けることは可能なのですが、だからといって適当に作成すればよいというわけではありません。
というのも、小学校によっては、願書の内容を踏まえて、受験生やその家族が学校の教育方針に賛同しているのかを推し量ろうとするからです。
小学校としては、当然ながら自分たちの方針に共感してくれる子供に入学して欲しいと考えるのが自然ですので、いくら試験の成績が良かったとしても、願書の内容がイマイチだと場合によってはご縁を頂けないということもあり得ないわけではありません。
せっかくの子供の頑張りを無駄にしないためにも、願書でビハインドにならないように、くれぐれも気合を入れて作成するようにしましょう。
願書作成のポイントとは?
次に、願書作成のポイントについて見ていくことにしましょう。
事前の学校研究を怠らないこと!
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という有名な孫子の教えがあることからも分かるように、何かを成し遂げるにはまずは相手のことをきちんと理解しなければなりません。
小学校受験であれば、いきなり願書を作成しようとするのではなく、学校研究を徹底的に行っていくというのが重要なのです。
そのためには、学校説明会や運動会などの外部者が見学可能なイベントには極力参加することはマストです。
それ以外にも、志望校のホームページや志望校について書かれた書籍などにはできる限り目を通しておいた方がよいでしょう。
特に、慶応幼稚舎や早実、学習院といった伝統校を受験する場合には、それぞれの教育方針を諳んじれるくらいになっておくのがおすすめです。
ちなみに、我が家の場合は、年中の頃から志望校の説明会には一通り参加するようにしていました。
早いタイミングで学校の方針を聞いたおかげで、時間をかけて理解することができましたし、年長時にもう一度参加することでよりその学校について深く知ることにもつながったので、これから受験される方は、ぜひ年中の時から説明会などに参加しておくことをお勧めします。
教育方針に合った体験を!
教育方針について理解できたところで、それに合った体験をしておくというのも重要です。
例えば、自然体験を重視した教育を行っている学校を受験するのであれば、キャンプなどを通じて子供が自然に慣れ親しむ機会を作っておくと良いでしょう。
そういった経験は、願書を作成する際に、自分たちがその学校の方針と合っているというアピール材料にも使えるはずです。
我が家の場合は、コロナ禍ということで大したことはできなかったので、家庭菜園やカエルの飼育などといったあまりインパクトのないネタで勝負しました。
作成時は背伸びをしないこと!
いざ願書を書くとなると、つい自分たちを立派に見せようと思いがちですが、必要以上に背伸びをしようとするとかえって逆効果です。
小学校の先生は、これまでにたくさんの願書を見てきていますので、無理をして事実を誇張したとしてもすぐに見透かされてしまいます。
また、実態と違ったことを書いた場合、面接で子供がそれについて質問されて答えられないという事態にも陥りかねません。
そのため、願書を作成する際は、変に事実を脚色せずにありのままを書くようにした方がよいのです。
もっとも、ただ闇雲に思ったことを書けば良いというわけではありません。
願書の指示に従った内容にしなければならないというのはもちろんのこと、それに加えて、自分たちが学校の教育方針を理解していることや、その方針に子供が向いているということを精一杯アピールするようにしなければならないのです。
努力の成果を見せよう
願書はこれまでの子育ての成果を志望校にアピールする場といっても過言ではありません。お子さんと一緒に二人三脚で取り組んできたことが、志望校で学ぶことによってより一層輝きを見せるという熱い想いを伝えるように自分なりのストーリーを組み立てて記載するとよいでしょう。
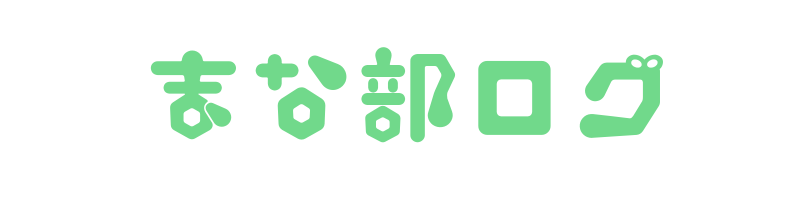
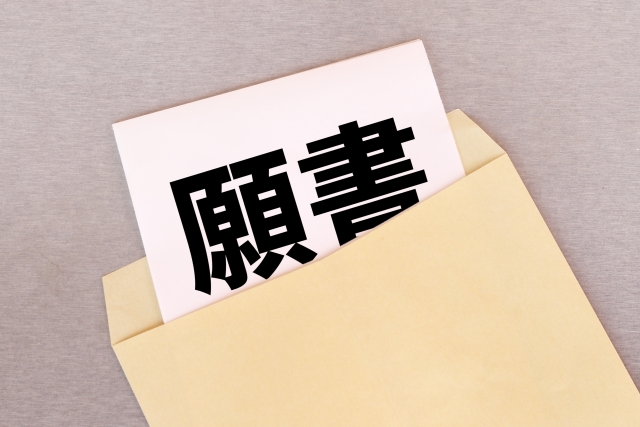


コメント